
右手のコントロールって基本でも有るけど奥義でもあるよね。
エレキギター、特にロック系のフレーズにおいてブリッジミュートで弾く機会はかなり多です。
低音弦でズンズンいわす重めの刻み、高音弦でタイトなシングルノートでのバッキング。
それらは基本のテクニックに分類されるんですが、これがかなり難しい。
- 1〜3弦と4〜6弦で右手のミュート位置がかなり変わる。
太い弦はある程度遊びが大きく、弦の振動も大きいので割と大雑把でも鳴りはするが、細い弦だとかなりシビアです。 - 低音弦は音の広がりをどこまで絞るかが難しい。
右手の位置でかなり音を変えられるが、あまりネック側によると音がシャープしてしまう。 - 高音弦は右手の位置次第で鳴らない場合が多い。
もはやただのミス。 - ピッキングのアップとダウンでも鳴り方が変わる。
アップピッキングが強目に引っかかりがちで不自然に音がハネてしまう。
これに更に音作りでも影響が出るので気を抜くとマジで変な音が鳴る。
僕はこれを基本テクニックと呼ぶのは無理があると思っている。
具体的な練習方法は思いつかないですが、やはり自分の音をよく聞く必要があるかなと。
自身が弾いている音がどんな風に鳴っているかを把握する、多分これは楽器の練習において必須の前提条件では位でしょうか?
やはり録音して聞いて確認が一番の正攻法なのかと、以前の記事になるがCubaseを使ったオーディオ録音の方法を書いたものがあるので、そちらも参照してみてください。
あとこの曲のAメロで1〜3弦のブリッジミュートのフレーズを多用してますのでよければご視聴ください。
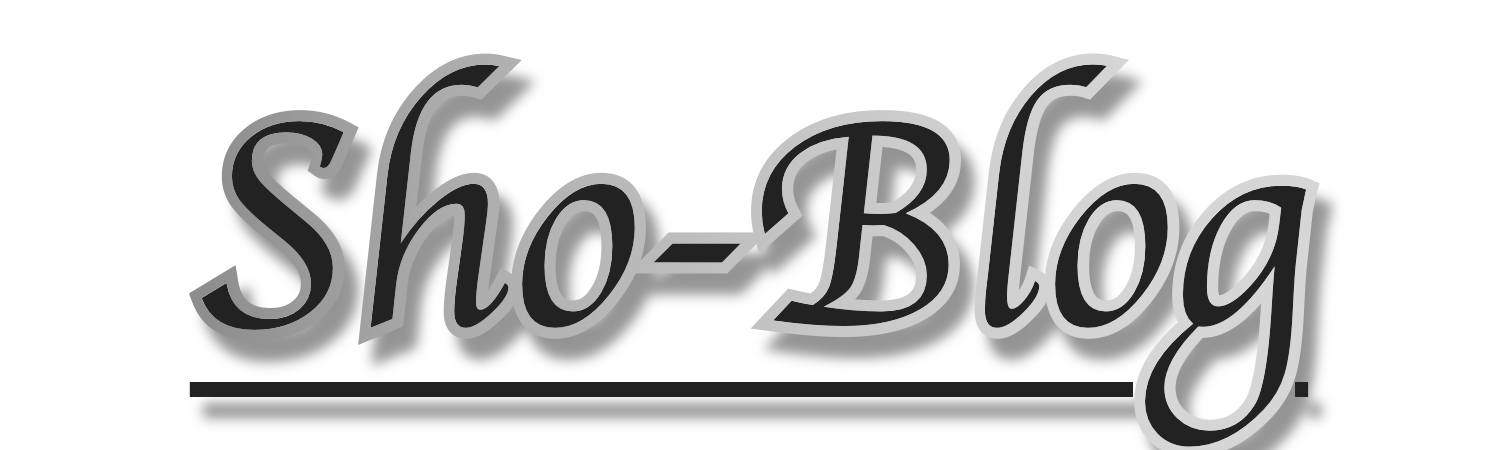

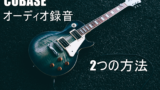


コメント